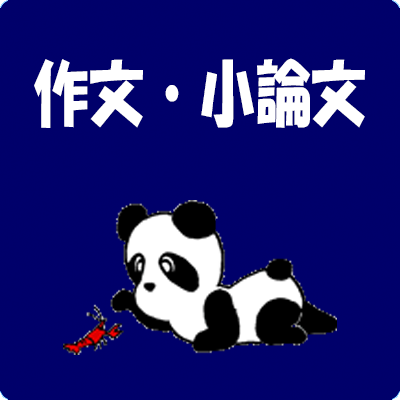新学習指導要領に出てくるCEFRとはⅡ
CEFR判定の際、評価の対象となるのは4技能5領域(言語活動)だけでなく、コミュニケーション能力(言語の働き)も含まれるというお話をしました。ではここで、CEFRではどのような判定方法がなされるのか、その判定方法について少しお話したいと思います。CEFR判定は、能力記述文(Can-do)で行われる
これまでお話したとおり、CEFRでは総合的な評価(例えば、あなたの〇〇語レベルはCEFRのB1です)の他に、4技能5領域やコミュニケーション能力についても細かく評価されます。そのCEFRのレベルを測るため『能力記述文』と呼ばれる参照枠(基準)が設けられています。これを英語で『Can-do(キャン・ドゥ)』と呼んでいます。100均ショップの名前ではありません(笑)。
それぞれのレベル、それぞれの技能にこれら『能力記述文(Can-do)』が用意されており、学習者、及び、先生たちはその『能力記述文(Can-do)』を使って判定(評価)します。サンプルとして『CEFR-J』を上げたいところですが、リンクをたどっていけば分かりますが、チェックが厳しいので誰でも自由に閲覧できる『日本語教育向けCan-doサイト』でお話しましょう。…あ、『日本語と英語は違うんだ』とか言わないでくださいね。前述したとおりCEFRは世界標準ですから英語も日本語も測る基準は同じです。
上のサイトからの例です。中学生・高校生が目指すCEFR‐A1~2レベルを見てみましょう。
まず4技能5領域と言いましたが、その4技能とやりとりにそれぞれ『能力記述文(Can-do)』が設けられています。青字をクリック(タッチ)すると、別窓でPDFがひらきます。
読む:読むCan-do
聞く:聞くCan-do
話す:話すCan-do
書く:書くCan-do
以上の4つが出来て中学・高校の英語をマスターしたということになります。また、前述のとおり、最終的な『やりとり』が重要ですのでもちろん『やりとり』についてもCEFRが設けられています。
やりとり:やりとりCan-do
いかがでしょうか?これが4技能5領域の判定基準です。では次にコミュニケーション能力に関する能力記述文(Can-do)も見てみましょう。こちらはJPEGにしてあります。
文法能力・言語構造的能力:言語構造的能力Can-do
文法能力・機能的能力:機能的能力Can-do
文法能力・テクスト:テクストCan-do
社会言語能力:社会言語能力Can-do
談話(ディスコース)能力:談話能力Can-do
方略(ストラテジー)能力:方略能力Can-do
このような『能力記述文(Can-do)』によって判定されるのです。こんなのどうやって評価するんだよ!
…なんて声が聞こえそうですね。
そこで用いられるのが『パフォーマンス評価』です。以下、私が実際に行っているパフォーマンス評価の(私の)例を、少し説明したいと思います。
パフォーマンス評価

これらの場合、本当に読めた(理解できた)のか、本当に聞き取れた(理解できた)のかは、学習者自身にしかわかりません。先生が『分かりましたかぁ~?』と聞いて、生徒たちが『分かりました!』と答えるのが、いかにアテにならないのかは良く知っています(笑)。
ですので、私が学生の英語能力(又は、日本語能力)を判定する際、『受容』に関してはペーパーテストで判定し、それをCEFRに当てはめるようにしています。また『言語知識』もペーパーテストで判定しますが、これはCEFRに当てはめられませんので、日々の学習状況、及び、学習成果の参考とする程度です(上図青い枠)。
では、他の2つは?
残りの『話す』と『書く』のことを『産出』と言います。
『産出』を評価する際、ペーパーテストでは無理です。作文を添削して苦し紛れに点数化する試みは行われてきましたが、もっと良い評価方法があります。それが『パフォーマンス評価』です。この評価は特に『やりとり(活動)』で威力を発揮します(上図赤い枠)。
まず、先生たちは、生徒たちの英語能力を評価する際、これらCEFRの『能力記述文(Can-do)』の中から、評価の観点を探します。
ここでは以下の『やりとり』を例にやってみましょう。
やりとり:やりとりCan-do
まずは、上(↑)の『能力記述文(Can-do)リスト』から、評価の観点とする能力記述文を選びます。選ぶ『能力記述文(Can-do)』は、その授業で行うテーマや活動、学習目標から判断します。そして、選んだ『能力記述文(Can-do)』を元に以下のような表(ルーブリック)を作ります(※クリック(タッチ)すると別窓でPDFが開きます)。 縦の①~⑤が評価の観点となります。右側の『できる』『難しいがなんとかできる』『あまりできない』『できない』が評価基準となります。実はこれは私の日本語学校で実践したルーブリックなので4段階(点数)となっていますが、日本人の英語教育のCEFR-Jでは3段階となっています(詳しくは、住所氏名等の個人情報を入力し、パスワードをもらってダウンロードしてみて下さい)。
評価の観点のうち、①~③の3つの観点が『やりとり』の『能力記述文(Can-do)』になります。そして、④~⑤が、『やりとり』技能に含まれるコミュニケーション能力、『ストラテジー(方略)能力』と『ディスコース(談話)能力』を判定する評価の観点になります。これは後程ご説明します。
このルーブリックを学期はじめ、授業はじめ、学校行事等の前に配布します。もちろん『能力記述文(Can-do)』は、学習者の母語にも翻訳して提示します。このルーブリックが、その学期、その授業、その学校行事で身につける外国語の学習目標となります。
そして、その学期、授業、学校行事の修了後、そこで自分が使用した外国語(皆さんは英語)を各自が振り返り、自己評価して提出します。また、同時に先生たちも学習者の状況をしっかりと観察し、同じルーブリックに評価をつけます。
学生が自分でつけたルーブリック(評価)と先生の評価を比較します。当然、学生の評価と先生の評価が違うものも出てきます。その場合、同じ能力記述文に対し学生が(自分では)『できる』と判定しても、先生の判定が『できない』でしたら先生の判定を優先します。逆に学生が『できない』と判定したのに先生が『できる』と判定した場合、学習者の向学の意思を尊重し、『できない』と判定します。
あらかじめカリキュラム(またはシラバス)で設定した基準に基づき、ルーブリックの合計点数が8点以上の場合、そのレベルを『獲得』と判定します。これがパフォーマンス評価です。
上の例では、このうちの2つ『ストラテジー(方略)能力』と『ディスコース(談話)能力』をルーブリックに加えて判定しています。これらの外部(先生の)判定は、その言語を第一言語、ないし第二言語として習得した者でないと判定できません。『お受験英語』の言語知識詰込みでは判定は出来ませんし、身につけることも出来ません。
例えば『 社会言語能力CEFR-B1【CEFR441】』を見てみましょう。
これまで学校で教えて来た『お受験英語』で、こんなこと学習できるとお考えでしょうか?
そう。
薄々、感じられた方もいるかもしれませんが、これって、他の教科に当てはめてみて下さい。体育や音楽、美術、技術家庭の先生たちがやっている評価と同じなんです!
体育の成績はペーパーテストで決まりますか?
音楽の成績はペーパーテストで決まりますか?
美術の成績はペーパーテストで決まりますか?
その他、技術家庭、書道…、これらは『技能』であって、ペーパーテストでは判定できないのです。
もちろんペーパーテストも実施しますが、それは『知識』の部分であって技能(実技)の評価はパフォーマンス評価で行っているのです。
新学習指導要領が実施される前の英語教育とは、まるでこれら技能教科の先生たちがペーパーテストだけで成績判定するような、異常な教育だったのです(笑)!
英語で技能評価するのは難しい?
いいえ。何も知らないだけです。
海外留学しなければ無理?
そんなことはありません。プロの語学教師(インストラクター)の指導を受ければ大丈夫です。
お受験英語の世界しか知らないからこんな発想を持ってしまうのです。
新しく設定されたCEFRとは、これまでのような英語に関する『言語知識』の量を測る基準ではなく、その言語(英語)を使って何が出来るかといった、言語運用能力の熟達度、習熟度を判定する基準(標準)です。その判定は、4技能5領域だけではないのです。
| Tweet |